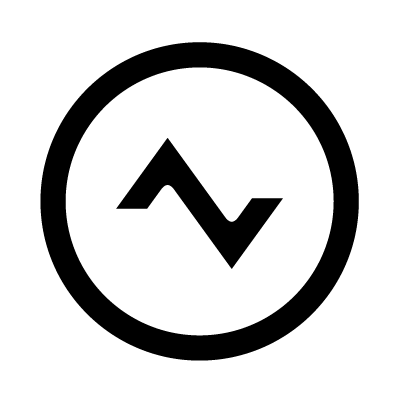マインドシェアとは? -ネオマーケティング-
ライター:株式会社ネオマーケティング
公開日:2022年03月09日
| 更新日:2023年11月15日
-
カテゴリー:
-
PR・プロモーション
マーケティングリサーチ
マインドシェアとはマーケティング用語の1つで、消費者の心(マインド)の中のブランド占有率を意味します。よく目にするものの、詳細については理解していないという方も少なくないでしょう。
今回は、
• マインドシェアとはなにか?
• マインドシェアを計測する方法
• マインドシェアを高めるための施策
について詳しく解説します。
マインドシェアとは消費者の心を締める割合が高いブランド
マインドシェアとは、消費者の心(マインド)のシェア率のことで「自社ブランドがどれくらい存在感があるか」を示す割合を意味する用語です。
アメリカのマーケティング戦略家であるアル・ライズ氏、ジャック・トラウト氏が1981年(日本では1987年)に発表した「ポジショニング」の中で提唱しました。
両氏は、「激化する競争の中においてブランドやアイディアが成功できるかどうかは、心の中のポジショニングで決まる」としています。
マインドシェアは認知度・好感度・重要度・チャネル力など複数の要素からなる概念で、ただ有名なだけでなくそのブランドに対してどのような印象を持っているかで決まります。
マインドシェアとマーケットシェアの関係
マインドシェアは心の中のブランド存在感ですが、マーケットシェアは市場のシェア率=売上の高いブランドのことを指します。ハーバード大学のマイケル・ポーター教授は、マーケットシェアを4つに分類しそれぞれの戦略の立て方を提示しました。
一方、前述のポジショニング理論において、マーケットシェアを広げるためにはマインドシェアを高める必要があると説かれています。
つまり、マインドシェアの高さは潜在的な市場シェア率とも言える部分もあるのです。
第一想起ブランドとマインドシェア
第一想起ブランドとは、純粋想起調査で一番最初に思い浮かべるブランドのこと。第一想起ブランドは検討・購入される可能性が高いとされ、トップ・オブ・マインドと言われています。もちろん、最初に思いつくからといってポジティブな印象を持たれているとは限りませんし、検討していく中で他のブランドを購入することもありますが、第一想起ブランドは検討者数・購入者数の両方を高めることが期待できるでしょう。
また、純粋想起・助成想起調査で得たデータを元に、視覚的にマインドシェアを分類するのが「トップオブマインド分析」です。
純粋想起率を縦軸、助成想起率を横軸とし、リーダー/レガシー/ニッチ/マイノリティの4区分に分けます。
・リーダー(勝者)
純粋想起率と助成想起率共に高く、ブランド認知度は4つのグループの中でももっとも高いブランドです。
マインドシェアの割合も高く、その認知度の高さを保つことが課題です。
・レガシー
助成想起率が高く、純粋想起率が平均よりも低いブランド。
普及はしているものの一番に思い起こすわけではなく、ヒントがあって存在を思い出す「かつて有名だった」的な存在です。
歴史が長いブランドである場合が多く、知名度はあるので、リブランディングが有効な施策と言えるでしょう。
・ニッチ
純粋想起率が高く、助成想起率が低いタイプのブランドがニッチに分類されます。
このカテゴリ名の通り一部の人から熱く指示されるニッチなブランドで、これから広く認知してもらうためのマーケティングが必要です。
・マイノリティ
純粋想起率、助成想起率共に低くマインドシェアが獲得できていないブランドです。
まずは現状をしっかりと把握し、なぜ認知度やマインドシェアが低いのかを理解することが、今後の戦略方針を決めるために大切です。
マインドシェアを高めるため大切なブランドコミュニケーション
マインドシェアを高めるためには、自社ブランドの魅力を伝えるためのブランドコミュニケーションが必要です。
具体的なブランドコミュニケーションの施策を3つご紹介します。
一貫したテーマとブランディング
マインドシェアを高めるためのブランドコミュニケーションは、「一貫性」が重要です。
我々は広告だけを見て商品を買おう!と決めるわけではなく、実際は口コミや評判を見たり、公式サイトで商品情報を詳しく見てから店舗で実物を見て決める・・・などいろんな形でブランドと接する機会を重ねてから購入を決めることが多いです。
接触する媒体によって、テーマや世界観がちぐはぐだと消費者のブランドへの好感度や信頼性は下がってしまいます。1から10まで一貫したテーマを提供できるように、ブランドのテーマや世界観を綿密に練り、スタッフ全員としっかり共有しましょう。
ブランド理念を社内にしっかりと浸透させるための施策としては、
• 上層部からの説明(キックオフミーティングや冊子など)
• 定期的な研修
• スキルや実績のコンテスト化
などが挙げられます。
広告やSNS
広告やSNSは大切なブランドコミュニケーションです。
• ブランド広告(ブランド自体の世界観やミッションをPRするための広告)
• プレス/PR活動(ブランドにふさわしい情報を戦略的にリリースする)
• 世界観を感じられるSNSプロモーション
などの施策は、ブランドローンチ時以外にも定期的に展開することでテーマや世界観の認知が進められます。
顧客体験
展示館やイベント開催も製品プロモーションだけでなく、ブランドの理解を深めるために効果的です。
• 展示会/リリースイベント
• セミナーやワークショップ
• レッスン体験
• パーティー
• 店舗接客
などは、消費者や顧客に対して体験を提供できる体験型マーケティングとして活用されています。
消費者は、物を所有するよりも「体験」が印象に残るとされており、複数の体験型マーケティングを組み合わせてより強く印象づけることもマインドシェアの向上に繋がるでしょう。
まとめ
マインドシェアはブランドの占有率のことで、このマインドシェアが高いとマーケットシェアが高い、あるいは高くなる可能性がある、マーケティングで大切な要素のひとつです。マインドシェアを得るには知名度や売上だけではなく好感度なども必要なので、簡単ではありませんが、適切なマーケティングにより向上が望めます。
合理的な施策を作成するためにも、定期的な認知度調査やフレームワークなどで認知度を把握していきましょう。
ネオマーケティングは国内約2450万人のアンケート会員を保有するパネルネットワークを構築、ご希望の調査対象者にリサーチを実施することが可能です。
マーケティング課題を解決し、必要なデータを取得するための調査設計から、調査結果の活用まで、伴走してご支援しています。リサーチを起点に、デジタルマーケティング、PR、ブランディング支援も行っています。
まずはネオマーケティングのサービス資料をご覧ください。
← マーケティングコラム一覧に戻る