市場にモノやサービスがあふれている現代において、商品開発が担う役割の重要性が増しています。競合他社にはない独自性を打ち出した商品や、顧客ニーズを深く汲み取った商品を開発したいと思いながらも、何から着手すればよいのか考え込んでしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、商品開発の基本的な流れと役立つノウハウを紹介します。よくある失敗を防ぐための注意点にも触れていますので、ぜひ商品開発に取り組む際に役立ててください。
また、ネオマーケティングでは、インサイトから商品コンセプトを創り出すサービスを提供しております。
ご興味のある方はぜひご覧ください。 >サービス資料をダウンロードする
そもそも商品開発とは
はじめに、商品開発とはそもそも何をすることなのかを整理しておきましょう。商品開発の意義と目的、開発する商品による違い、商品企画との違いを押さえてください。
●商品開発の意義と目的
商品開発に取り組む意義は、まだ世の中に存在しない商品のイメージを明確化し、商品コンセプトを言語化することにあります。単にアイデアを出すだけではなく、顧客ニーズを踏まえて商品を開発し、市場へ投入した後の売り方まで含めて設計することが商品開発の役割です。
世の中の多くの人は新しいものを求めています。新たなモノやサービスを開発することで新規顧客を獲得すれば、新たな収入源につながります。さらに、多くの顧客から認知されれば商品を提供する企業の認知度が向上し、ブランド価値を築くこともできるのです。
●商品開発の種類
商品開発には大きく分けて次の3種類があります。
1.新規商品の開発
既存商品とは異なるイメージ・コンセプトの新しい商品を開発します。多くの人が商品開発の仕事内容として想像するのは、主に新規商品の開発でしょう。
2.既存商品の改良
まったく新しい商品の開発だけでなく、既存商品を改良することも商品開発に含まれます。顧客ニーズに応えるために小規模な改良を加えることもありますが、既存商品のイメージやコンセプトを大胆に変更するケースも少なくありません。
3.ラインナップの増強
商品のシリーズラインナップを増強するために、色やデザイン・機能性などのバリエーションを増やすこともあります。シリーズ全体の商品イメージ・コンセプトを保ちつつ、より幅広い顧客ニーズに応えるための商品開発といえるでしょう。
●商品企画との違い
商品開発と商品企画はよく似た言葉ですが、担うべき工程が大きく異なります。
- 商品開発:商品のイメージやコンセプトを具体化すること
- 商品企画:商品のイメージやコンセプトを考案すること
商品開発の前工程が商品企画にあたると考えてください。商品企画はあくまでも考案段階までを担当するため、提案通りに商品化が実現するとは限りません。一方、商品開発の場合はイメージやコンセプトを打ち出すだけでなく、実際に商品として形にする段階や市場に投下する段階まで含めて担当します。
商品企画と商品開発を別部門としている企業も見られますが、同一部門内で企画・開発を担当するケースも多いのが実情です。この場合、商品開発に商品企画の役割も含まれていると捉えてください。
商品開発の進め方6ステップ
一般的に、商品開発は次の6ステップで進めます。各ステップの目的を押さえつつ、全体の流れを把握しましょう。
- 市場分析
- ターゲティング
- 商品コンセプトの決定
- マーケティング施策の決定
- 商品化とテストマーケティング
- プロモーションと市場投下
1.市場分析
商品開発の目的は「作りたいもの」ではなく「市場が求めているもの」を開発することにあります。まずは市場を深く理解し、自社が入り込む余地があるか十分に検討しておかなくてはなりません。次の観点で市場分析を行い、新規参入が可能な市場機会があるか見極めてください。
【市場分析の観点の例】
・市場規模
・ニーズの有無
・競合他社の状況
・自社が提供できる強み
競合他社が存在しない市場は、そもそもニーズが低い可能性があります。反対に、ニーズが顕在化している市場ほど多数の企業が参入しており、レッドオーシャンになりがちです。一定のニーズが存在し、かつ自社の強みが発揮できる確率の高い領域を見つけましょう。
2.ターゲティング
参入する市場の候補が定まったら、次に行うべきことはターゲティングです。ターゲティングは「誰に価値を提供するのか」と言い換えてもよいでしょう。以下に挙げるような観点で消費者のセグメンテーションを行い、注力するべき層を絞り込んでおく必要があります。
【セグメンテーションの例】
- 地理的変数:居住地域、生活圏など
- 人口統計的変数:年齢、性別、職業、家族構成など
- 行動変数:購買状況、行動パターンなど
- 心理的変数:嗜好、趣味、価値観など
ターゲットを広げたほうが取りこぼしを防げると考えがちですが、これは誤っています。ターゲットを十分に絞り込んでおくことで、商品コンセプトを定めやすくなるのです。
3.商品コンセプトの決定
ターゲティングが「誰に価値を提供するのか」を指すのに対して、商品コンセプトは「どのような価値を提供するのか」を指します。商品を購入することで得られる便益(ベネフィット)を次の3つに分け、商品コンセプトを築いていきましょう。
- 機能的便益:商品がもたらす効果や利便性
- 情緒的便益:商品がもたらす心理面への良い影響
- 自己表現的便益:商品を利用することで得られる自己イメージ
たとえば、開発する商品が「スマートウォッチ」の場合を考えてみます。数多くの先進的な機能を搭載したスマートウォッチは機能的便益を満たしてくれますが、これだけでは十分とはいえません。心拍数測定や転倒検知といった機能によって、より安全で健康的な暮らしが手に入るという情緒的便益を提供できます。さらに、最新鋭のウェアラブルデバイスを身につけることに対する進歩的な自己イメージが、商品の魅力をいっそう高めるのです。
4.マーケティング施策の決定
たとえニーズに応える商品を開発しても、売るための仕組みや戦略がなければ購入してもらうことはできません。消費者の心理や行動を予測し、購入に至る道筋を先回りして用意しておく必要があります。マーケティング施策とは、こうした一連の仕組みをあらかじめ築いておくことを指しているのです。
商品の販売価格や販売ルート、広告・宣伝の方法など、検討しておくべきことは多岐にわたります。商品そのものを創り出すだけでなく、売り方やPRの方法も商品開発に含まれていることを押さえておきましょう。
5.商品化とテストマーケティング
開発した商品は、市場に投入する前に地域や販売ルートを限定してテストマーケティングを実施するのが一般的です。
【テストマーケティングの例】
- 会場テスト:調査会場で複数の消費者に商品を試してもらい、反応や感想を収集する。
- ホームユーステスト:商品を自宅に送付し、一定期間試してもらった上で感想を聞く。
テストマーケティングで得られた消費者の声を商品に反映させ、改良を図ります。想定していた市場性とずれがないか確認するとともに、より実態に即した商品開発を行う上でテストマーケティングには重要な意味があるのです。
6.プロモーションと市場投下
商品を本格的に市場へ投下する前に、プロモーションを実施しておくことが非常に重要です。多くの消費者は未知の見慣れない商品を進んで購入しません。商品そのものの良し悪し以前に、商品を認知しているかどうかが購入可否を決定づけるケースも少なくないのです。商品を知ってもらうための施策として、以下の4点が挙げられます。
【プロモーション施策の例】
- 広報・パブリシティ:プレスリリース、自社メディア・SNSでの告知など
- 広告・宣伝:Web広告、SNS広告、動画広告、TVCMなど
- 販売促進:クーポン配布、懸賞の告知、ポイント付与、サンプリングなど
- 口コミ:SNSでの拡散など
プロモーションは複数の施策を同時並行で進めることで相乗効果がもたらされます。さまざまな方法で商品の認知度を高めた上で、商品を市場に投下しましょう。
商品開発に取り組む際に役立つノウハウ
商品開発の6ステップのうち、とくに「市場分析」「ターゲティング」「マーケティング」に役立つノウハウを紹介します。商品開発に取り組む際には、ぜひ取り入れてください。
●3C分析
市場分析においては、企業視点ではなく顧客視点に立った分析が求められます。顧客理解に役立つノウハウとして活用されるのが3C分析です。3Cとは、Customer・Competitor・Companyを表しています。
- Customer(顧客):顧客にとって
- Competitor(競合):他社よりも優れた価値を
- Company(自社):提供できる自社の強みとは?
顧客理解を深めるために、調査を実施するケースも少なくありません。インターネット調査やグループインタビュー、デプスインタビュー(=1対1で実施するヒアリング調査)を通じて、顧客が感じていること・期待していること・不満に感じていることなどを聞き取っておくとよいでしょう。
●5フォース分析
市場分析の際に3C分析と併せて活用したいのが「5フォース分析」です。5フォースとは5種類の脅威を表しています。外部環境を多方面から分析することにより、自社の競争優位性を探る際に役立つのです。
- 既存競合他社の脅威:顕在化している競合関係
- 新規参入企業の脅威:参入障壁を元に分析
- 代替品の脅威:業界外から代替品が供給される可能性
- 売り手の脅威:サプライヤーとの力関係
- 買い手の脅威:顧客との力関係
昨今は製品サイクルが短期化しており、現時点での競争優位性を分析するだけでは十分とはいえなくなっています。3C分析と併せて5フォース分析を活用することにより、より長い時間軸で商品の収益性を見通しやすくなるでしょう。
●STP分析
ターゲティングに役立つのがSTP分析です。STPとは次の3要素を表しています。
- Segmentation(セグメンテーション):市場を細分化する
- Targeting(ターゲティング):狙いを定める市場を決定する
- Positioning(ポジショニング):自社の立ち位置を見極める
ターゲティングにおいては、「誰に価値を提供するのか」を検討すると同時に「自社はその価値を提供可能か」を十分に検証しておく必要があります。STP分析を通じて自社の強みがより明確になり、商品コンセプトの立案へとつながる道筋を見いだしやすくなるのです。
●マーケティングミックス
マーケティング施策を決定する際には、マーケティングミックス(4P)の視点で検討する必要があります。
- Product(製品):機能性、デザイン、パッケージ、保証、アフターサービスなど
- Price(価格):消費者にとって妥当な価格帯と上限価格、価格設定と販売量の予測など
- Place(流通・販売ルート):どこで商品を販売するか、卸販売か直販かなど
- Promotion(広告・宣伝・販売促進):商品に関する情報を消費者に届ける手段
マーケティングはプロモーションと混同されがちですが、プロモーションはあくまでもマーケティング施策の一環です。4Pを複合的に検討し、商品を売るための仕組み全体をデザインすることがプロモーション戦略の成否を分ける重要なポイントと捉えてください。
商品開発に取り組む際の注意点
商品開発に取り組む際には、いくつか押さえておきたい注意点があります。次に挙げる3点は、商品開発に欠かせないスタンスとして社内で共有しておきましょう。
- 自社のブランドコンセプトを共有しておく
- リリース後もPDCAを継続する
- 社外のリソースを積極的に活用する
●自社のブランドコンセプトを共有しておく
商品開発には複数の部門が関わるケースがほとんどです。部門や担当者によって自社のブランドコンセプトに対する認識が異なると、商品開発の方向性にブレが生じる原因にもなりかねません。
商品開発に取り組む前に関係者間で認識の統一化を図り、自社のブランドコンセプトに対する共通認識を形成しておきましょう。担当者の個人的な見解や好みが商品開発に反映されることのないよう、前提となるブランドコンセプトを十分に確認しておくことが大切です。
●リリース後もPDCAを継続する
商品開発はリリースがゴールではありません。むしろ、リリース後に市場の反応を確認しながら調整をかけていくことによって、商品力を最大限に引き出せるはずです。
顧客アンケートや流通各社から挙がってくる意見を収集し、必要に応じて機能の追加や品質改善を図りましょう。また、営業・販売担当者へのヒアリングから改良のヒントが見つかる場合もあります。このように、リリース後もPDCAを回し続けていくことで商品開発の精度を向上させ、ノウハウを蓄積していくことが重要です。
●社外のリソースを積極的に活用する
商品開発は試行錯誤の連続ですが、できるだけ早期に成功事例を築き上げ、モデルケースとして活用していくことも大切です。既存のノウハウやリソースのみを頼りに解決を図ろうとするのではなく、社外のマーケティング支援サービスを積極的に活用しましょう。
とくに市場分析やプロモーションは、準備段階で大きな負荷がかかるケースもめずらしくありません。社外のリソースを活用することで、より効果の高いリサーチやプロモーションの手法を最短距離で導入できるでしょう。
商品開発の事例紹介
ネオマーケティングでは、デザイン思考に立脚した独自のリサーチサービス「インサイト・ドリブン」を提供しております。既存の枠に留まらない顧客視点の商品開発の手法にご興味のある方は、ぜひ下記ホワイトペーパーをご覧くださいませ。
また、実際に導入して頂いた企業様の事例も掲載しておりますので、併せてご覧ください。
まとめ
市場にモノやサービスがあふれている現代において、商品開発が担う役割の重要性がいっそう増しています。今回紹介した6ステップの進め方と役立つノウハウを参考に、商品力の増強を実現してください。
ネオマーケティングでは、国内外を対象としたネットリサーチをはじめ、会場調査やホームユーステストの支援サービスを提供しています。また、デザイン思考に立脚した独自のメソッドである「インサイト・ドリブン」により、既存の枠に留まらない顧客視点の商品開発にも対応可能です。商品開発に注力したい事業者様、マーケティング戦略を強化したい事業者様は、ぜひネオマーケティングにご相談ください。





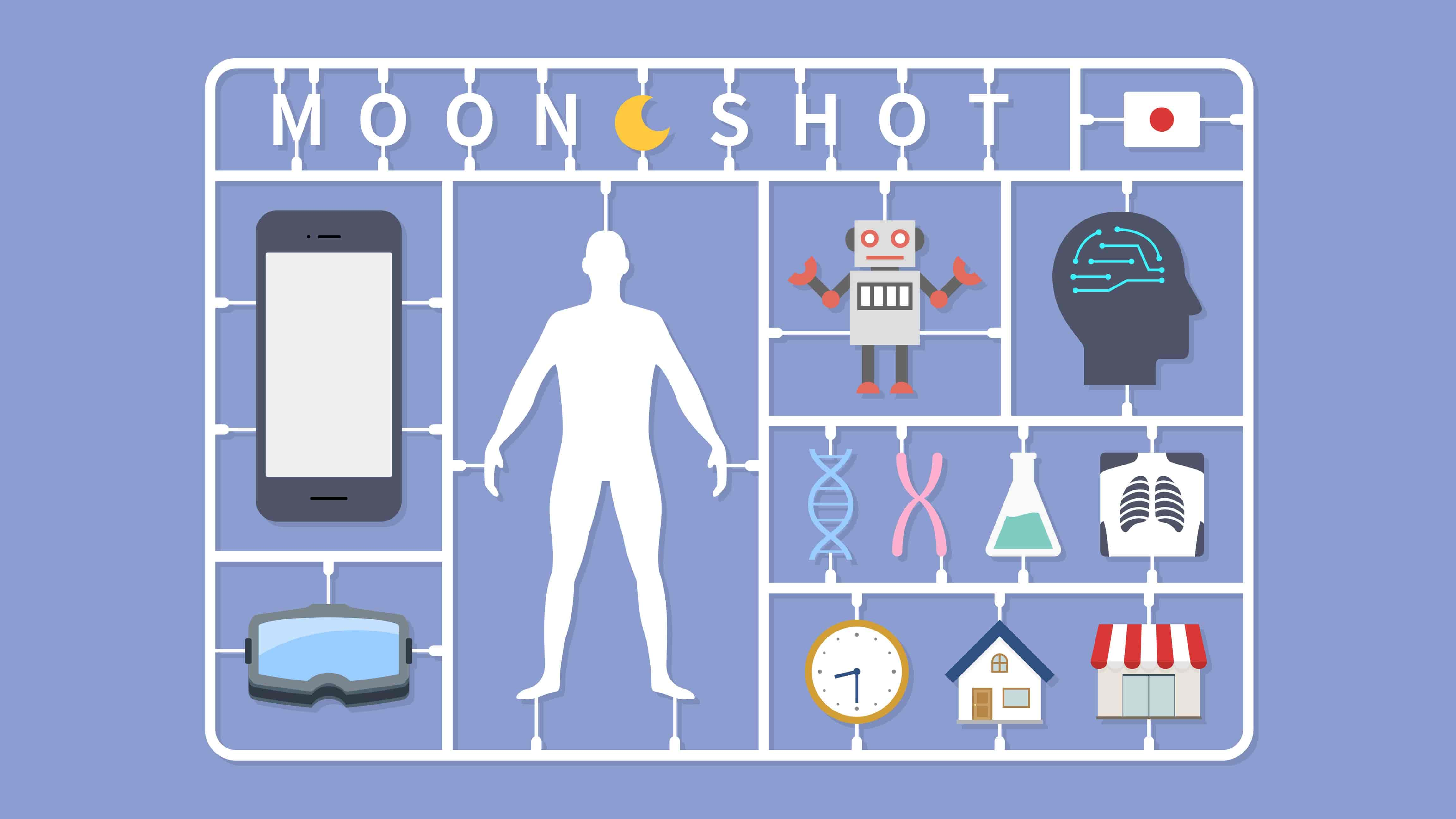


.png)