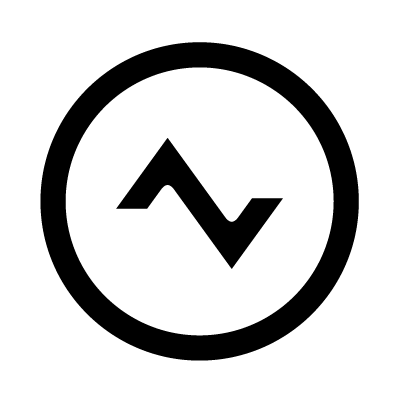近年、消費者が手軽に情報を得られるようになったことに伴い、商品コンセプトの重要性が増しています。かつてのように「良いものを作れば売れる」時代ではなくなり、商品イメージや消費者にとってのベネフィットを明確に伝える必要に迫られているのです。
今回は、商品コンセプトのフレームワークを実際の商品事例とともに紹介します。商品コンセプトを作る上で押さえておくべきポイントや具体的な調査方法にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
ネオマーケティングでは、商品コンセプト開発のリサーチサービス「インサイト・ドリブン」を提供しています。ご興味のある方は、下記よりサービス詳細をぜひご覧ください。
>「インサイト・ドリブン」紹介資料をダウンロードする
商品コンセプトとは
商品コンセプトとは、「どのような商品か」「誰が使うものか」「ベネフィットは何か」を言葉や図で端的に表したものです。商品開発の起点となるのはアイデアですが、アイデアだけで商品化に漕ぎ着けることはできません。アイデアを具現化し、消費者へ届けるための道筋を立てる必要があります。アイデアを発展させ、消費者に届けるべきメッセージとして集約したものが商品コンセプトといえるでしょう。
●商品コンセプトの重要性
商品コンセプトの重要性が増している主な理由は、商品ライフサイクルの短期化です。現代社会においては、市場にモノやサービスがあふれており、消費者が購入できる商品の選択肢は増加の一途をたどっています。商品の機能デザインによって優位性を打ち出し、競争力を維持するのは困難といわざるを得ません。
消費者に商品を見つけてもらい、選んでもらうには「なぜその商品が必要なのか」を可能な限り素早く理解してもらう必要があります。そのためには、ターゲットが必要としている価値と実際に提供できる価値を一致させる必要があるでしょう。消費者に提供する機能面のベネフィットだけでなく、情緒面でのベネフィットも踏まえて商品開発を進める上で、商品コンセプトは非常に重要な位置を占めているのです。
●有名な商品コンセプトの成功例
よく知られている商品コンセプトの成功例として、「本麒麟」と「Dyson」を紹介します。いずれも大ヒット商品であり、多くの消費者の心をつかんだ事例として広く知られていますが、成功の背景には優れた商品コンセプトがあったのです。
・本麒麟
第3のビールに消費者は何を求めているのかインタビュー調査を繰り返し実施したところ、消費者は「ビールらしさ」を求めていることが判明しました。味やパッケージ、コミュニケーションに至るまで「ビールらしさ」を軸に商品コンセプトを固めた結果、ヒット商品となった事例です。消費者の本音に徹底的に迫り、ニーズに対して本気で応えたことがヒットの秘訣といえるでしょう。
・Dyson
世界初のサイクロン掃除機で知られるDyson。「吸引力が変わらない」という有名な商品コンセプトの原点となったのは、従来の掃除機に対する消費者の不満でした。年月を経るごとに吸引力が弱まっていく掃除機に、不満を抱えている消費者が多いことを知った創業者ジェームズ・ダイソン氏は、消費者の不満点を解消することがベネフィットに直結すると考えたのです。結果として商品のベネフィットが非常に明確になり、圧倒的なブランディングの実現にも成功しています。
商品コンセプトの創り方
商品コンセプトを作成する際には、一般的に次の手順を踏む必要があります。
- 商品アイデアの発案
- ターゲットの決定
- 事業規模の想定
- 商品アイデアの検証(独自性・競合優位性)
- 消費者にとってのベネフィット検証
- 商品イメージの策定
- トレンドの調査と整合性の検証
- 商品化に向けた具体策の検討
商品コンセプトがまとまるまでに検討・検証すべき点が複数あることから、抜け漏れなく効率的に進めることが大切です。
●コンセプトシートの作成
商品コンセプトを効率的に策定するための工夫として、コンセプトシートの作成が挙げられます。コンセプトシートとは、商品コンセプトの核となる要素を記載した文書のことです。コンセプトシートを作成する主な目的を押さえておきましょう。
- 開発プロセスにおいて、商品の企画意図から逸脱していないかチェックする
- 消費者のニーズとアイデアの整合性が図られているか確認する
- 商品企画の意図・方針をチームやプロジェクト内で共有する
商品コンセプトについて議論していくうちに、当初の企画意図から逸脱してしまうケースは決して少なくありません。商品コンセプトがどのような経緯で策定されていったのかを言語化しておくことにより、企画意図から逸脱するのを防ぐことができます。また、チーム内・プロジェクト内での商品コンセプトの共有に活用することがコンセプトシートの主な役割です。
●コンセプトシートの例
コンセプトシートの作成を通じて、商品コンセプトを固めていく過程を実際に見ていきましょう。下図は、茶飲料の商品アイデアから商品化までの過程をまとめた一例です。
- 商品アイデア:体脂肪を減らす効果のある茶飲料
- ターゲット:
・体脂肪が気になっている方
・健康習慣を取り入れたい方
- 事業規模:首都圏のコンビニにてテスト販売後、全国のコンビニで販売
- 商品の独自性・競合優位性:ペットボトル緑茶でトクホ
- 消費者にとってのベネフィット:毎日1本飲むだけで体脂肪に効く
- 商品イメージ:健康に役立ちたいという願いを込めた商品
- トレンドの調査と整合性:
・男性は30代以降、女性は50代以降の3人に1人が肥満
・健康志向の高まり
- 商品化に向けた具体策:
・高濃度茶カテキン540mg配合
・1本160円(350ml)
|
商品コンセプトを作る上でのポイント
商品コンセプトを作る際には、商品そのものの価値に着目するのではなく「消費者にとってのベネフィット」に重視することが大切です。消費者にとってのベネフィットとは、消費者自身が実感する「進歩」を指します。進歩を実感するには、そもそも原点となる課題や問題意識が必要です。
前述の茶飲料の例では、「体脂肪が気になっている」「健康習慣を取り入れたい」といった課題を消費者が抱えており、潜在的に解決策を求めているからこそ、「体脂肪を減らす効果のある茶飲料」という商品コンセプトが成立しています。提供する価値が企業側の独りよがりにならないよう、消費者のニーズを起点に商品コンセプトを考案していくことが大切です。
商品コンセプトの調査方法
消費者の視点に立った商品コンセプトを策定するには、そもそもニーズが存在するのか、市場のトレンドと整合性が取れているのかを調査しておく必要があります。調査を通じて実際に商品化を進めるべきか、見合わせるべきかを判断することが重要です。商品コンセプトの調査方法には、大きく分けて定量調査と定性調査の2種類があります。
●定量調査
定量調査の代表的な手法として、アンケート調査が挙げられます。質問票を配布し、回答者には選択式で回答してもらうのが一般的です。定量調査でよく用いられる質問(評価軸)には、次の項目があります。
| 質問項目 |
質問例 |
| 購入意向 |
この商品を購入したいと思いますか? |
| 興味関心 |
この商品に興味が湧きますか? |
| 独自性 |
他にはない商品であると感じますか? |
| 新規性 |
この商品に新しさを感じますか? |
| 魅力度 |
この商品が魅力的であると感じますか? |
| 共感性 |
ご自身の価値観や生活スタイルに合っていると思いますか? |
| 理解度 |
商品の特徴や利便性が良く分かりますか? |
| 信頼性 |
この商品は信頼できると感じますか? |
それぞれの項目について、「非常にそう思う」「どちらかといえばそう思う」「どちらでもない」「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」の5段階の回答を用意するとよいでしょう。回答結果から、より重点的に改良するべき点や訴求すべき点の分析に役立つヒントが得られます。
後述する定性調査ほど回答の意図を深掘りすることはできないものの、集計が容易で調査結果をスピーディに得られる点が定量調査のメリットです。
ネオマーケティングでは、アンケート調査によるコンセプト調査のサービス「ACT」を提供しています。
質問項目を独自の指標で標準化しているため、スピーディに調査を実施することが可能です。
PDCAを早く回したい方や、意思決定に繋げたい方は、下記サービスページをぜひご覧ください。
>コンセプト調査を標準化したサービス「ACT」をみる
●定性調査
定性調査の代表的な手法はインタビュー調査です。対象者から1人ずつ回答を得るデプスインタビューや、複数人から同時に回答を得るグループインタビューなどが挙げられます。また、調査目的によっては行動観察調査(エスノグラフィー)や、オンラインインタビューといった手法が採られるケースも少なくありません。
定量調査にはない定性調査のメリットは、回答者の意識や感情をより深掘りし、消費者のインサイトを探ることができる点です。顧客理解を深めると同時に、商品開発につながる新たなヒントやアイデアを得るには適した方法といえます。定量調査と定性調査を組み合わせることで、消費者のニーズを多面的に分析しやすくなるでしょう。
ただし、定性調査を適切に実施するには対象者の選定や結果分析の客観性の担保など、いくつか越えなくてはならないハードルがあるのも事実です。調査サンプル数も限られることから、ごく一部の消費者の意見に過ぎないという点にも注意する必要があります。マーケティング会社に依頼するなど、専門的な知見を持つ外部事業者のサービスを活用するのが得策です。
ネオマーケティングでは、定性調査において「新商品コンセプト開発サービス」を提供しています。生活者のインサイトを基に、新商品コンセプトを創り上げるサービスです。既存の商品開発方法に課題を感じている方、新しい方法を探している方は、ぜひ下記資料をご覧ください。
商品コンセプトの事例紹介
最後に、実際に弊社にてエクストリームユーザーの調査行い、商品開発に活用した事例を紹介します。
●株式会社セブン&アイ・ホールディングス様
- 課題:様々なカテゴリーのブランディングを行っている中で、競合他社のPBと「同質化」している
- 実施内容:ネットリサーチ、エスノグラフィー、ワークショップ
- 結果:課題があったカテゴリーのリブランディングのヒントを得ることができ、商品開発に活用することができた
まとめ
市場にモノやサービスがあふれ、商品ライフサイクルが短期化している現代においては、ターゲットが求めている価値と提供できる価値を一致させる必要があります。商品コンセプトを固めた上で商品開発を進めることで、より消費者ニーズを捉えた商品の投入が可能になるでしょう。
今回紹介した商品コンセプトの作り方や企業の事例を、ぜひ商品企画を考案する際に役立ててください。消費者に届けるメッセージが明確化されることによって、これまで発見されていなかったニーズを掘り起こせるはずです。