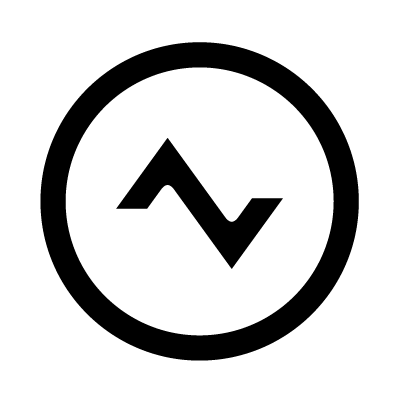近年、クリエイティブ分野だけでなくビジネスにおいても「デザイン思考」という言葉が広く使われるようになりました。デザイン思考とは具体的にどのような思考法なのか、活用することでどういったメリットを得られるのか、疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
今回はデザイン思考について、特徴や他の思考法との違い、フレームワークを紹介します。デザイン思考を取り入れた企業の事例も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
ネオマーケティングでは、デザイン思考を取入れた商品開発支援サービス「インサイト・ドリブン」を提供しています。エクストリームユーザーを調査してインサイトを創り上げ、商品コンセプトを創り上げるリサーチサービスです。商品開発の新しい取り組みに興味のある方は、下記資料をぜひご覧ください。
<「インサイト・ドリブン」の紹介資料をダウンロードする>
デザイン思考とは?
はじめに、デザイン思考とはどのような思考法を指すのか、定義や特徴を確認しておきましょう。デザイン思考が注目されている背景についても併せて押さえておくことが大切です。
●デザイン思考の3つの特徴
デザイン思考とは、もともとデザイナーやクリエイターが制作過程で用いていた思考プロセスを応用した思考法です。未知の状況や前例のない課題に対して、ゼロベースから最適な解決策を考える際に用いられます。ビジネス領域におけるデザイン思考の主な特徴は次の3点です。
- ユーザーの共感や満足感を主軸とする
- 課題の定義と解決意図を明確にした上で試行錯誤を繰り返す
- 前例や先入観を排除してゼロベースで思考する
ビジネス領域には過去の事例がもたらしてきたセオリーやロジックが数多くありますが、こうした枠組みを意図的に度外視し、バイアスを取り去った状態から思考を始める点が大きな特徴といえるでしょう。
●デザイン思考が注目されている背景
デザイン思考が注目を集めている背景には、急速に変化しつつある市場の状況があります。従来、商品開発においては消費者のニーズをリサーチし、リサーチ結果を元に仮説を立てて検証していく仮説検証型のアプローチが一般的でした。市場の細分化が進み、消費者の興味関心がいっそう流動的なものとなった現代においては、固定的な仮説を検証しているだけではニーズに応えるのが難しくなりつつあるのです。
より本質的なニーズの「核」を捉えるには、目の前の事象に囚われない柔軟な発想が欠かせません。先入観を排してゼロベースで思考を深めていく手段として、デザイン思考が注目されているのです。
デザイン思考と他の思考法との違い
クリエイティブ領域やビジネス領域にはデザイン思考以外にもさまざまな思考法が存在します。デザイン思考と他の思考法との違いを整理しておきましょう。
●アート思考との違い
デザイン思考はもともとクリエイティブ領域で発達してきた思考法のため、同じくクリエイティブ領域で用いられる「アート思考」と混同されがちです。しかし、アート思考とデザイン思考には大きな違いがあります。
アート思考は「作り手側」に軸足を置く思考法です。アート作品の制作であればアーティスト、ビジネス領域であれば事業者の発想が起点となっており、創出されたアイデアが世の中に受容されるかどうかは必ずしも重要視されていません。一方、デザイン思考は「受け手側」である消費者のニーズを起点とする思考法です。発想の起点が大きく異なる点に注意してください。
●ロジカルシンキングとの違い
ビジネス領域においてよく活用される「ロジカルシンキング」に関しても、デザイン思考とは大きく異なるアプローチと捉える必要があります。
ロジカルシンキングとは「論理的思考」のことです。思考を整理する際に論旨を明確にし、ロジックの裏付けがあるかどうかが重要視されます。一方、デザイン思考はクリエイティブな発想を重視する思考法です。従来型の発想から自由な立ち位置で思考を深められるかどうかが重視されます。このように、ロジカルシンキングとデザイン思考では、重視すべき思考プロセスや思考を深める際の立ち位置が大きく異なっているのです。
●クリティカルシンキングとの違い
クリティカルシンキングとは「批判的思考」のことです。事象をあるがままに受け入れるのではなく、あえて批判的な視点から疑問を見出し、検証していくことを指します。企画・開発の当事者である企業にとって、見落としやすい欠点や不十分な点を発見する際に役立つ思考法です。
一方、デザイン思考においては「共感」が重要な要素とされています。消費者の立場になって想像力を働かせ、「自分がユーザーだったら」「ユーザーにはどう映るのか」といった視点から思考することが求められるのです。クリティカルシンキングとデザイン思考では、求められるアプローチが異なる点を押さえましょう。
デザイン思考の5段階のプロセス
スタンフォード大学のハッソ・プラットナー・デザイン研究所は、5段階のプロセスに分けてデザイン思考を実践する方法を提唱しています。ただし、各プロセスは1から順に進める必要はなく、途中で行き来したり同時並行で進めたりしても構いません。あくまでも思考プロセスをより捉えやすくするための分け方と考えてください。
●1.共感(Empathize)
デザイン思考の根底にあるのは「共感」です。自社のサービスやプロダクトをユーザー視点で捉え、ユーザーがどのように感じるか、相手の立場になってゼロベースで捉え直しましょう。ユーザーへのアンケート調査やインタビューを実施した場合は、回答の背後にある心理や感情面も含めて理解を深めることが大切です。まるで他人事のように考えることがないよう、自身もまた1人のユーザーという認識のもと、自分事として捉える必要があります。
●2. 定義(Define)
ユーザーニーズを深掘りし、解決すべき課題を設定します。すでに顕在化している表面的なニーズに留まらず、ユーザーが深層心理で抱えているニーズを深掘りしていくことが非常に重要です。顕在化していないユーザーの心理・感情や、言語化されていない背景にも着目しましょう。
こうして導かれた本質的なユーザーニーズを元に、解決すべき課題を仮説として定めます。以降のプロセスで仮説が適切でないと判断した場合には、1・2のプロセスに立ち返り仮説を設定し直してください。
●3. 創造(Ideate)
仮説を元にアイデアを出し、ユーザーの課題を解決するためのアプローチを決めていきます。ニーズに対して表面的に応える方策を考えるのではなく、ニーズの根本にある欲求を満たす方法を追求することが大切です。あくまでもユーザーの視点に立って解決策を講じることを念頭に置きましょう。
ユーザーの視点を取り入れてアイデアを創造するために、共創型ワークショップを開催してユーザーの声を直接聞くのも有効な方法です。企業側の先入観に囚われた解決策へと安易に着地することのないよう、ユーザー主体の視点を常に意識することが大切です。
●4. 試作(Prototype)
試作品を制作して、アイデアを一度形にします。プロトタイプの段階ではクオリティにこだわるのではなく、できるだけ時間とコストをかけることなく形にすることを重視してください。
良いアイデアのように思えても、実際に形にしてみると懸念点が複数挙がってくるケースは決してめずらしくありません。むしろ改善点を挙げることが試作の目的のため、「形にする」「懸念点を挙げる」「改善する」サイクルのスピード感を重視しましょう。
●5. テスト(Test)
ブラッシュアップしたプロトタイプによるユーザーテストを実施します。開発に携わったメンバーが見落としていたポイントが見つかったり、企業側が想定していなかった使い方をするユーザーが現れたりすることもあるはずです。
テストの段階においても、ユーザー視点にもとづく共感を重視することが大切です。ユーザーテストで挙がった意見を表面的に捉えることのないよう、相手の立場に立ってニーズの本質を探り、必要に応じて2〜5のプロセスを繰り返しましょう。
デザイン思考のメリット・デメリット
デザイン思考をビジネスに取り入れることによって、どのようなメリットを得られるのでしょうか。デザイン思考を闇雲に取り入れるのではなく、具体的なメリット面を把握した上で効果的に導入する必要があります。また、デザイン思考によるデメリット面についても併せて押さえておきましょう。
●デザイン思考のメリット
デザイン思考の主なメリットは次の4点です。
- 潜在ニーズの発見に適性がある
- 不確実性の高い状態でリスクを管理できる
- チームや組織の共通言語として活用できる
- 妥当性のある定性調査の実施が可能
デザイン思考は課題解決のための思考法です。言い換えるなら「顧客体験の最適化を図るマインドプロセス」と表現できるでしょう。そのため、必然的に「消費者の行動はどのような思考から生まれたのか」といった、消費者自身も気付いていない「潜在ニーズ」の発見や、「インサイト」の創造につながります。
なお、潜在ニーズの発見につながるデザイン思考の特徴と、限られた対象者を深く理解するための定性調査との相性は非常に高いといえます。ただし、定性調査を実施する際には限られた調査対象者のリクルーティングを慎重に行うことが重要です。偏った調査結果にもとづいて消費者ニーズを推測することのないよう十分注意しましょう。
●デザイン思考のデメリット
デザイン思考を取り入れることで、デメリットとなりかねないのは次の4点です。
- 技術開発には向かない(ユーザー候補の発見には活用可能)
- 高い学習意欲が前提
- 関係者同士の継続的な相互貢献が不可欠
- 日常業務と違う行動原則
デザイン思考は商品開発に適している一方で、技術開発には向いていません。潜在ニーズから導き出されるのは「どのような技術が必要か」ではなく、「どのような商品・コンセプトが求められているか」という点だからです。潜在ニーズに応える商品を開発できる技術を保有していることが、デザイン思考を活用する際の前提条件といえます。
また、デザイン思考は従来ビジネスで活用されてきたノウハウやフレームワークとは大きく異なっています。マーケティング施策や商品開発にデザイン思考を初めて活用する場合、これまで築いてきた仕事のやり方・考え方を大きく変える必要に迫られるでしょう。携わるメンバーに高い学習意欲が求められるだけでなく、社内および関係者同士の相互理解も必要になるはずです。こうした環境面の整備がハードルになりやすい点は、デザイン思考を取り入れるデメリットといえます。
デザイン思考と関連の深いフレームワーク
デザイン思考を実践する際に役立つ可能性のあるフレームワークを紹介します。デザイン思考をサポートする思考法として、ぜひ活用してください。
●デザインスプリント
創出されたアイデアの本質的な価値や、顧客体験に与える影響を検証する際に用いられるフレームワークです。一般的に5日間ほどの期間で実施し、理解・発散・決定・プロトタイプ・テストの5ステップで進められます。
デザインスプリントは、デザイン思考を業務プロセスに組み込むことを主な目的として考案されました。したがって、短期間で集中的にデザイン思考のトレーニングを行う際にも活用できます。デザイン思考を初めて取り入れる企業にとって、「デザイン思考とはどういうものか」を体験する機会となるでしょう。
●バリュープロポジションキャンバス
高い顧客ニーズが存在するにもかかわらず、競合他社が十分に価値を提供できていないポイントを発見し、自社独自の価値を打ち出していく際に用いられるフレームワークです。デザイン思考のプロセスのうち、共感・定義を経て創造のフェーズへと移る際によく用いられます。
顧客理解を深めるための顧客プロフィールや、自社が創造・提供すべき価値を可視化するためのバリューマップを作成するのが一般的な進め方です。両者が重なるポイントを見出すことにより、独自の価値を提供するためのアイデア創出へとつなげましょう。
●ビジネスモデルキャンバス
これから手がけるビジネスの全体像を把握するためのフレームワークです。事業の構成要素や全体の構造が可視化されることから、既存事業の改善を図る際に用いられるケースが多く見られます。
デザイン思考ではユーザーニーズを主軸としてアイデアを創出するため、ビジネスサイドから見た場合に実現性が不透明になるケースは少なくありません。創出されたアイデアをビジネスモデルキャンバスにプロットしていくことによって、不足している点や再考すべき点を洗い出せるでしょう。
●共感マップ
ユーザーの思考・行動・価値観などをマッピングし、整理するためのフレームワークです。エンパシーマップとも呼ばれます。ユーザーをマップの中心に位置づけ、次に挙げる6つの視点からユーザーを分析するのが一般的な進め方です。
- ユーザーが考えていること・感じていること
- ユーザーが耳にしていること
- ユーザーに見えているもの
- ユーザーの発言・行動
- ユーザーが抱えている痛み・ストレス
- ユーザーにとって得られるもの
デザイン思考の軸である「共感」を可視化する作業を通じて理解を深めるとともに、プロジェクトに携わるメンバー間で共感のイメージを共有できます。
●ジャーニーマップ
ユーザーが商品・サービスとどのような関わり方をするのか、一連のプロセスを時系列で可視化するためのフレームワークです。ジャーニーマップは以下に示すように構成します。
- 縦軸:ユーザーの要素(行動・タッチポイント・思考・感情・課題)
- 横軸:ユーザーのフェーズ(認知・興味関心・比較検討・購入)
デザイン思考を通じて創出されたアイデアが、実際のユーザーにどのような形で受容されるのかを時系列で把握できます。強化が必要なフェーズや戦略の抜け漏れを発見できるため、施策の精度を高めることにつながるでしょう。
デザイン思考を効果的に活用するポイント
デザイン思考を効果的に活用するには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。次に挙げる3点をデザイン思考の原則として念頭に置き、プロジェクト等に関わるメンバー間で周知徹底を図ることが大切です。
●人間中心設計
デザイン思考はプロダクト中心ではなく、人間中心の設計を原則とする必要があります。ここでいう人間とはユーザーのことです。ユーザーの視点に立って本質的な課題を発掘し、課題に対して根本的な解決策を探る必要があります。
裏を返すと、アイデアの着想が企画・開発側の論理にもとづいていないか、プロダクトありきの発想になっていないか、常に注意深くチェックしていくことが大切です。あくまでも人間(ユーザー)を中心に据えて考えるという点に注意しましょう。
●共創型
共感を軸とするデザイン思考では、特定の考え方や感覚にもとづいてアイデアを創出するべきではありません。さまざまな立場の人や異なる経験をもつ人の価値観に寄り添い、想像力を働かせることが欠かせないのです。
デザイン思考を取り入れるのであれば、プロジェクトメンバーに多様な人材を投入する必要があるでしょう。異なる意見や考え方、価値観をもつ人々が対話を重ねることで、共創型のプロジェクトを推進していくことが大切です。
●非線形プロセス
非線形とは、互いに比例関係にない状態のことを指します。「〇〇によって売上が伸びる」「〇〇が良い効果をもたらす」といったように安易に関連づけるのではなく、プロセスそのものを重視する点が大きな特徴です。
たとえば、一度定義したユーザーニーズを再考したり、試作・テストを経て「ユーザー視点とは何か?」をあらためて捉え直したりすることもあり得ます。このように、手戻りを恐れずプロセスを自由に行き来できることがデザイン思考の強みでもあるのです。
デザイン思考取入れた商品開発事例紹介
デザイン思考について興味はあるけど、いきなり取り入れるのは不安という方に向けて、前述した弊社のサービス「インサイト・ドリブン」に取り組んでいただいた企業様の事例をご紹介します。デザイン思考を取入れて、どのようにマーケティング施策に活用したかについて、インタビュー形式でお話いただきました。ぜひご覧ください。
①株式会社セブン&アイ・ホールディングス様
<事例概要>
- 課題:様々なカテゴリーのブランディングを行っている中で、競合他社のPBと「同質化」しているという課題
- エスノグラフィーを実施したことで、これまで見えてなかった発見があった
- エスノグラフィーで得た情報を、ワークショップでインプット・意見交換をして今後の方針を決定した
- 結果、課題を持っていたカテゴリーのリブランディングのヒントを得ることができ、商品開発に活用することができた
②清原株式会社様
<事例概要>
- 目的:ユーザーからの「直接買いたい」という要望に応えるべく、D2Cサイトの立上げをする
- ネットアンケートでの市場調査、その結果をもとにデプスインタビューを実施。
- 上記で得た情報を基に、社内でワークショップを実施
- キャッチコピーやボディコピーの作成、写真撮影を経てD2Cの運用をスタート。
まとめ
デザイン思考はユーザーへの共感を追求し、本質的なニーズを探る上で有効な思考プロセスといえます。一方で、従来ビジネスで活用されてきた一般的なフレームワークやスキームとは大きく異なるのも事実です。デザイン思考の特徴やメリット・デメリットを理解した上で、適切に取り入れていく必要があるでしょう。
ネオマーケティングでは、デザイン思考を取り入れたマーケティングソリューションサービス「インサイト・ドリブン」を提供しています。
ご興味のある方は、ぜひ下記資料をご覧ください。